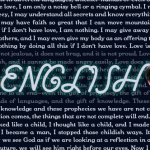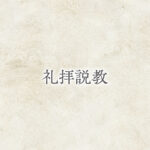聖書箇所
<ヨハネによる福音書5章39~40節>
<テモテへの手紙Ⅱ3章10~17節>
聖書には私たちを導いてくれる貴い言葉がちりばめられています。深い「知恵」を示す言葉もあれば、慰めに満ちた「癒し」の言葉もあります。前回の説教で引用した<フィリピ書>に、「へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい」<2章3節>という言葉がありましたが、幼稚園の先生がこの言葉を聞きながらしっかりとうなづいておられました。自分の日常に生かすべき言葉と思われたのかもしれません。今月の教会学校早起き礼拝の子どもたちの暗誦聖句は、クリスマスによく引用される、「おめでとう、恵まれた方。主があなたとともにおられます」<ルカ福音書1章28節>という天使ガブリエルから主イエスの母マリアへの祝福の言葉ですが、K校長は5月の「母の日」にちなんでこれを選ばれました。たしかに「母親」を祝福する言葉としても意味があります。聖書の言葉は豊かなイメージの中で色々と応用も効く言葉です。これから聖餐式で読みます「疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう」<マタイによる福音書11章28節>という言葉も、私たちを慰め励ましてくれる言葉です。多くの方がこの言葉によって救われてきたために、聖礼典でも引用される言葉となったと思われます。
「ためになる良い書物」としての聖書?
このように、聖書には素晴らしい言葉を沢山見出すことができます。宗教的なことを念頭に置かなくても、ためになる言葉が多くありますから、クリスチャンでない方でも「聖書はいいですねえ」となるわけです。聖書をこのように「ためになる良い書物」と考えていただけるのももちろん歓迎すべきことですが、しかしキリスト教徒としてそこで留まってしまっては不十分かもしれません。キリスト教信仰にとって「聖書」とは何かということをしっかりと理解しておくことがやはり大切なことと思われます。そこで今朝の説教では、キリスト教信仰にとって聖書とは何か、その本来の使命は何だろうか、ということをお話ししたいと思います。そこで、この説教のためのテキストとして取り上げたのが、<ヨハネによる福音書5章39~40節>と<テモテへの手紙Ⅱ3章10~17節>です。
さて、その本題に入る前に、この説教作成への私自身の直接の動機となったことをお話ししますと、それは前回の「聖書に親しむ会」で、司会のH姉が掲げられた「旧約聖書と新約聖書の比較」というテーマでした。いつもは聖書中の一書かその一部分が参加者の熟読と黙想のためのテキストとして指定されるわけですが、その会では以上のテーマが掲げられたわけです。実際には参加メンバーの愛読、愛誦の旧新約の箇所を披露し、それについて色々分かち合って終わりましたので、このテーマを深掘りするところまでは行きませんでした。
旧約聖書への疑問
しかし、なぜ、いつもとは違って、こういうテーマをH谷姉が掲げられたのか。旧約と新約の比較というわけですから、そこには両書の違いが前提されています。教会の信徒どうしの会話の中で、旧約聖書にはキリスト教的とはとても思えない内容があってどうしてもなじめない、旧約の神さまは厳しい裁きの神さまで恐ろしささえ感じる、どうしてそんな内容の旧約聖書がキリスト教信仰を導く経典なのだろう、といった声を聞いてきたし、自分にもそういう思いがないわけではない、できることならその疑問をすっきりと晴らしたい――というわけで、H谷姉はこうしたテーマを掲げられたのではないか、というのが、私自身の穿った見方です。ただ、その中味は、前回の会では、今申しましたように、深掘りの議論にまでは至らなかったのですが。
旧約聖書を読んでの驚きということで言えば、たしかに、<エレミヤ哀歌>には、戦争による飢餓という限界状況であったとは言え、母親がその子を煮炊きして食べたという記事があることは、私の何回かの説教で言及してきましたし、最近、CS中学科でサウルとダビデの物語を学んでいるときに、戦争で勝利したら敵も全滅させ戦利品も殲滅せよというのが神からの命令であったということを知らされました(これを学者たちは「聖絶」と呼んでいるようです)。例えば、このように、旧約聖書には現代の私たちには違和感を覚えざるをえない異なる考えや出来事が多く記されております。
キリスト教の「正典」としての旧新約聖書
しかし、そうした側面をたしかにもつ旧約聖書も、新約聖書とともに、信仰を導く正規の経典である、というのが、キリスト教の正統的な立場です。日本基督教団の信仰告白に「旧新約聖書は…教会の拠るべき唯一の正典なり…信仰と生活との誤りなき規範なり」とあるとおりです。ただ、そうは言いましても、今申しましたように、正直に言えば、キリスト教徒たちは旧約聖書に対して以上のような疑念を依然として抱いている、という現実があります。こうした二律背反をどのように信仰において整理し、納得を得ることができるかというのが、現代のキリスト教徒としての課題であるわけですが、本日の説教が皆さんのその課題克服のための一助になればと願います。
旧約聖書を排除したマルキオン
今、旧新両約聖書がキリスト教信仰のための「正典」である、と申しましたが、このキリスト教の公式の立場は教会の歴史の中で成立してきたものです。初めからそうした考えが出来上がっており、そこからキリスト教は出発した、というわけではありません。実は紀元二世紀前半にトルコ人で、旧約聖書大嫌い!の、マルキオンというキリスト教徒がおりました。彼の意見を簡潔にまとめますと、旧約聖書の神は律法の神、それを守らない者には怒りの神であり、この神が造った世界も苦しみの世界である。これに対し、主イエスが示した神さまは唯一真(まこと)の神、慈しみと憐みに満ちた神であり、主はこの神の愛によって罪人を救って下さった方である、ということでした。そして、この観点から、キリスト教信仰にとって旧約聖書は不要と考え、当時すでに流布していた新約文書の中でも「ルカ福音書」と九つの「パウロ書簡」だけを正典としました(しかもこれらの書にも自ら改変の手を加えました)。こうした考えの背後には彼のユダヤ人嫌い、現代で言う「反ユダヤ主義(アンティ・セミティズム)」もあったと思われます。
聖書文書の「正典」化
初代教会にはこのような動きがあり、教会は信仰の基準を定める必要を痛感して、時間もかかりましたが、信仰文書の「正典」化へと進んで行きました。「正典」と訳されるCanonという語は元来「葦」を表わすエジプト語(カノネー)由来の英語で、葦の茎の「節」がほぼ一定の長さだったところから「尺度」を表わす語となり、ついには「正典」という用語に選ばれたわけです。そこで、この正典化の歴史も簡潔に申しますと、キリスト教会は、ユダヤ教が紀元90年代初めの「ヤムニア会議」でその正典と確定した39の旧約文書をやはり自身の旧約聖書として受け入れ、その後紆余曲折を経て27のキリスト教文書を新約聖書として確定し、三九七年の「カルタゴ公会議」でこれら六六巻を旧新両約聖書すなわちキリスト教の「正典」として決定しました。聖書の最後の書<ヨハネ黙示録>が、「これに付け加え」てはならない、「取り去って」もならないと言うとおりです<18~19節>。
聖書―ーイエスをキリストと証しする「最も信頼のおける第一証言者」
さて、以上のことを申し上げたうえで、キリスト教信仰にとって「聖書とは何か」という本題に入りますと、<ヨハネ福音書5章39節>が申しますように、聖書は「わたし〔イエス・キリスト〕について証しをするものだ」ということです。<ヨハネ福音書>は、主イエスの直接の証言として、この言葉を記しています。キリスト教徒にとってこれ以上明確な聖書の本質の指摘はありません。聖書はナザレのイエスをキリストすなわち救い主と証しするキリスト証言なのだと、主イエスご自身が言われたのです。そこで、教会は、これまで聖書を、イエスをキリストと証しする第一にして、最高の、すなわち他のいかなる証言にも優る、証言者と理解してきました。
その際、気をつけたいのは、ここで主イエスが「聖書」と言われているのは、もっぱらいわゆる「旧約聖書」のことであったということです。主イエスの時代に新約文書はありませんでした。のちに記された新約聖書をイエス・キリストの証言と理解することはもちろん正しいわけですが、主イエスが言われた「聖書」とは旧約聖書のことです。つまり、旧約聖書もイエス・キリストの証言であり、そうならばやはりクリスチャンはマルキオンのようにそれを正典から除外することはできないのです。
神の霊に導かれつつ「人によって」書かれた書物
もう一点、聖書はキリストの証言者である、ということから自覚しておくべきは、信仰にとって聖書自体は神さまではない、ということです。それは当然のことだと言う方がおられるかもしれませんが、キリスト教会には聖書がまるで神であるかのように聖書を重んじてきたグループがありました。「聖書信仰」Bibelglaubeとか「聖書主義」Biblicismといった表現はこれらグループによる聖書の絶対視の傾向を示唆しています。気をつけならねばならない点です。キリスト教徒は神を信じるのであって、聖書を信じて拝むのではありません。だから、聖書は朗読するのであって、「聖書を拝読します」という表現は用いないほうがよい、と言われた東神大の先生の言葉が、今も忘れられません。
以上の、聖書そのものは神ではない、という点が、今朝この説教のために掲げました<テモテへの手紙Ⅱ3章10~17節>の聖句の内容にも関わってきます。16節には「聖書はすべて神の霊の導きの下に書かれ」とありますが、要点を明らかにするために私なりの表現を挿入しますと、ここは「神の霊の導きの下に人によって書かれ」たもの、となります。聖霊の導きのもと、信仰をもって記したものであっても、その記者は不完全な人間であるゆえに、結果として聖書の中には不整合で納得のいかない記述も存在しているわけです。N姉が、礼拝の聖書朗読者として、<創世記1章26節>の「我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう」という箇所を読むとき、聖書の神さまは唯一神と信じているので、とても違和感を感じます、と仰るのに対して、それについてはあらためて神学の講義を致しますのでお聞き下さいと言うのもまどろこしく、聖書にも困ったもんだ、と呟いております。
以上、聖書が抱える問題性について指摘してきましたが、しかし、そうであるにもかかわらず、聖書のために弁明しなければなりません。すなわち、聖書はたしかに人が記したものとしてそれなりの限界を示しています。しかし、イエス・キリストに対する、第一の、最も信頼のおける、証言者である、ということは間違いありません。他のいかなる人間的証人も、あるいは文書的資料も、この聖書に優るキリスト証言は存在しないのです。「されど」聖書、「さすが」聖書、なのです。
旧約聖書に垣間見える多神教の現実や記述
さきほど言及しました<創世記1章26節>はたしかに多神教的宗教文書からの引用文なのではないか、「さすが」聖書なのであれば、なぜ唯一神教の立場からここを編集していないのか、と問われますと、反論しようのない箇所です。実は<詩編>の中にも複数の神々に言及している箇所があります。<82編1節>、<89編1節>にも、「神々」と出てきます。しかし、これらの箇所は、聖書の本来の「神」ヤハウェがそれらの神々に優っている、それらを裁く立場におられる、と述べている箇所です。宗教学では、多神を同時に信じる「多神教」から、多神中の統括神を優先的に信じる「単一神教」へと進み、ついに唯一神を信じる「唯一神教」に達したとする説がありますが、今触れました<詩編>のテキストは単一神教段階を示している箇所と言えるかもしれません。いずれにしましても、旧約聖書の人々もやはりそうした段階を経て、「わたしをおいてほかに神があってはならない」<出エジプト記20章3節>という「唯一神信仰」に達したではないか、というのが、私の理解です。
キリスト教信仰は歴史の中で練磨されつつ完成を目指す
そして、そこからわかることは、キリスト教信仰というものは、信仰者たちの久しい歴史の中で切磋琢磨され、練磨されてきたものであり、いまだ完成途上にあるものと考えるべきではないか、ということです。そして、そうした見方をすれば、旧約聖書の人々の信仰態度は、例えば神をどうとらえるかという「神論」の観点からは玉石混交の状況にあった、と言えるのではないかと思います。人々のその「石」の部分がそのまま正直に記されているところに嫌悪感を覚えることになるのかもしれません。しかし、そこから「玉」が磨かれてきました。まるでふるいにかけられるように、多くの神々に心奪われることなく、ただヤハウェの神のみに純粋に信頼する人々が精錬され精選されて、唯一神信仰に達したのです。一部の旧約聖書学者たちはその過程を丹念に描き出しております。旧約にしばしば見られる「残りの者」という言葉はまさにこの信仰者たちの苦闘と練磨とを証言する表現です。
私たちは新約聖書後の時代に生きており、その信仰も新約のメッセージを土台に形造られたものであって、旧約の人々の信仰と比べれば、より純粋なキリスト信仰のはずだと、理屈上言うことはできるかもしれませんが、しかし正直に自身の信仰の中味を反省してみるなら、けっしてそう簡単に言うことはできないことに気づくはずです。その意味で、私たちの信仰も、それが本物のキリスト教信仰なのかどうか、この歴史の中でなお試され、練磨されている最中の、信仰なのです。
「苦難の僕」としてのメシア像
ただ、しかし、神は時至ってすなわち「お定めになった計画により」<使徒言行録2章23節>、主イエスを「主…またメシア」<同2章38節>として私たちの救いのために賜りました。弟子ペトロは「あなたはメシア、生ける神の子です」<マタイによる福音書16章16節>と告白しました(口語訳聖書では「あなたは生ける神の子キリストです」となっていました。「メシア」のギリシア語訳が「キリスト」です)。そして、この主イエスが、ご自身の究極の「メシア」像をもって、キリスト教信仰の最も肝心な点を明らかにして下さいました。自身が、メシアとはいかなる存在か、という「キリスト論」を示して下さったのです。私たちの信仰生活全体はいまだ鍛錬され磨き上げられるべきものですが、それはこの「原点」にしっかりと立ってなされるべきものなのです。それを外しては、「キリスト教信仰」にはならないからです。では、その肝腎な点とは何でしょうか。
一言で申しますと、それは、私たちが信じる救い主とは「苦難の僕」としてのメシアである、ということです。「メシア」という旧約聖書のヘブライ語は元来「油を注がれた者」という意味であり、人々は「王」を選ぶ儀式において神からの聖霊を表わす油の注ぎを行ないました。そこから、「メシア」は世俗の政治的支配者を意味する語として用いられるようになり、主イエスの時代にも人々が待望していたのは政治権力を帯びた世俗的な王としてのメシアでした。弟子のヤコブとヨハネの兄弟が、その母とともに、「王座にお着きになるとき」、二人をあなたの右と左に座らせてください<マタイによる福音書20章21~22節>と願ったことも、当時の人々が信じ続けていたメシアのイメージを如実に伝えております。
しかし、主イエスは、こうした旧約聖書の従来のメシア像は「真のメシア」を表わしてはいないと信じておられました。「異邦人の間では、支配者…が…権力を振るっている。しかし、あなた方の間では…偉くなりたい者は、皆に仕える者になり…すべての人の僕になりなさい」と言われ、さらに、私は「多くの人の身代金〔口語訳では「あがない」〕として自分の命を献げるために来たのである」と明言されました<マルコによる福音書10章42~45節>。ここに、それまでの旧約の人々や他民族のメシアのイメージとは決定的に異なる、主イエスご自身の「メシア」像が示されています。
そして、弟子ペトロは、主イエス亡き後、「あなたがたが十字架につけて殺したイエスを、神は主とし、またメシアとなさった」、それは「めいめい…罪を赦していただ」くためであったと説教しています<使徒言行録20章36、38節>。初代教会も、主イエスのメシア理解に従って、主イエスの十字架上の死の真の意味は多くの人々の「罪の赦し」のためであったと説いたのです。
こうして、主イエスが示された「メシア」の姿とは、権力を振るう「王」のそれではなく、人々の罪の償いのために彼らに代わって自らの命を差し出し、そうして彼らに罪の赦しを得させる「僕」のそれであった、ということがわかります。そこで、次に出てくる問いは、このメシア像はどこから来ているのか、ということです。人々は旧約聖書の多くの預言から人々を支配する「王」なるメシアのイメージを得ていたわけですから、以上のような主イエス独自のメシア像は旧約にはないものなのでしょうか。いや、そうではありません。
「バビロン捕囚」後になされたイザヤの「苦難の僕」預言
主イエスの時代より500年以上も前に、旧約の人々が「バビロン捕囚」の憂目に会い、幸いにも神のお導きによってそこから故郷に帰還することができたとき、預言者イザヤは、神は「疲れた者に…大きな力を与えられる」<イザヤ書40章29節>と、人々を励ます預言を行ないました。そして、これらの人々の中からメシアとしての「輝かしい風格も」ない一人の僕が現われ、ついには「捕らえられ、裁きを受けて、命を取られ」るが、しかし、
「彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちはいやされた」<イザヤ書53章2、8、5節>、
「彼は多くの人の罪を負い、咎ある者のためにとりなしをした」<同53章12節-口語訳>
という、実に不思議な預言を残しました。これが「苦難の僕」と呼ばれているイザヤの預言の箇所です。実に不思議というのは、この預言はまさに五百年後の主イエスの十字架の出来事とその死の意味を指し示しているように思われるからです。バビロン捕囚は旧約の人々に「苦難」を経験させ、その意味について深く考えさせたふしがあります。
ところで、主イエスが<イザヤ書>に精通しておられた様子は、安息日の会堂でこの書を引きながら説教しておられたと福音書が伝えるところからも、よくわかります<マルコによる福音書7章6節><マタイによる福音書一5章7節><ルカによる福音書4章16節>。ですから、主イエスは明らかにこの<イザヤ書53章>のメッセージをご存知でした。そして、そこにご自分の運命とその意味を重ね合わせられたということは大いに考えられることです。
主イエス亡き後、ペンテコステの聖霊の注ぎと励ましを受けて、初代教会は福音宣教に勇躍乗り出していくわけですが、その際主イエスの十字架の死の意味を説くにあたって、初代教会の人々もこの<イザヤ書〔53〕章>に依拠していたということは、先のペトロの十字架をめぐる説教や、とりわけフィリポによるエジプトの宦官に対する伝道の様子から、伺い知れます。この宦官はキリスト教に関心を抱き、旅の途中、何と<イザヤ書>を「朗読して」いたというのです。そこで、フィリポはここぞとばかり「口を開き、聖書のこの箇所〔イザヤ書〕から説き起こして、イエスについて福音を告げ知らせ」た、とあります<使徒言行録8章26~40節>。
このように、<イザヤ書>、とくにその53章が、主イエスの――従ってまた、初代教会の――「メシア」像を規定した実質であったということは疑いえません。そして、ここから教えられることは、主イエスご自身が旧約のこの特別な預言に基づいてそのメシア理解を確立され、初代教会もまたそれに従って自分たちの信仰を確立していったということです。その意味でも、旧約聖書はキリスト教信仰にとって不可欠のメシア証言であり、正典になくてならない構成部分だ、ということが言えます。もちろん、<イザヤ書53章>の預言は旧約全体から見れば極小部分ではないか、という批判的意見もありうるかと思います。しかし、それは数量的にすぎない見方であり、<イザヤ書>のこの箇所にこそ旧約聖書のメシア預言全体の意味の真髄が結晶化されていると、私は考えております。旧約の人々の信仰的経験全体の核心がここに集中的に表わされていると思うのです。
十字架――神の義と愛のあえるところ
私の最も好きな讃美歌の歌詞の一つが262番の第一節「十字架のもとぞ いとやすけき、神の義と愛のあえるところ」です。十字架は神の義と愛の会えるところなのです。聖書が証しする「神の義」とは、幸せに生きよと神が命を与えて下さった人間が、その主なる神に逆らい、罪に堕し、しかも己を救うにも無力の窮地に陥った、そこに神自身が憐みのうちに無償の救いの手を伸べられた、ということです。罪人にとり無償であるのは、父なる神がその独り子の命を十字架にほふるという犠牲の代価を払われたからに他なりません。そして、これがそのまま「神の愛」と呼ばざるをえない恵みの出来事です。こうして、十字架とは「神の義」がそのまま「神の愛」として表わされている恩寵の出来事なのです。
旧約聖書は信仰の苦闘の経験の末にこの究極の「神の義」を指し示しているキリスト教の経典であり、新約聖書はそれがナザレのイエスの十字架の死と復活により「神の愛」としてたしかに実現されたと宣言するキリスト教の経典です。そして、両書は相俟って、キリスト教信仰の貴い「正典」となるのです。
終