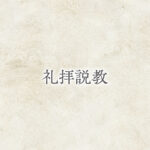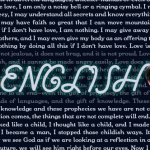愛する兄弟姉妹の皆様、今日はヨハネの福音書と手紙から、神様の愛とその機会について考えてみましょう。
今から102年前、アメリカでは「母の日」が国の祝日となりました。その起源は、ウェスト・バージニア州の小さなメソジスト教会で日曜学校の教師をしていたジャービス夫人が、「あなたの父母を敬え」という十戒の教えをもとに、生徒たちに「お母さんに感謝する方法を何か考えてください」と、勧めたことにさかのぼります。彼女の死後、娘のアンナは母の記念会を開き、母の好きだったカーネーションを参加者に配りました。この温かい試みが全米に広がり、日本でも、クリスチャン実業家の森永太一郎さん(森永製菓の創業者)によって広められました。
私自身の母も20年前に亡くなりましたが、母は聖書の言葉をよく暗唱していて私に聞かせてくれました。文語訳ですが、「しかはあれど、主を待ち望む者は新たなる力を得ん。また鷲のごとく翼を張りて昇らん。走れども疲れず、歩めども倦まざるべし。」(イザヤ書40:31)という御言葉を口に出して、「信仰に押し出されて・・・」祈るのが母の常でありました。
さて、イエスが最も愛した3人の弟子(ペテロとゼベダイの子ヤコブその兄弟のヨハネの三人)がおりました。そのヨハネは、後にエフェソで異邦人伝道に力を尽くしました。エフェソには、この「使徒ヨハネ」と「長老ヨハネ」の二つの墓が残っています。長老ヨハネは、使徒ヨハネの教えを受け継ぎ、イエスの福音を教会の仲間に書きとらせ、それが『ヨハネによる福音書』の原典となったと言われています。紀元120年頃のことであります。
一方、今日読んだ『ヨハネの手紙二』は、冒頭の挨拶で「長老」と名乗っていることから、「使徒ヨハネ」ではない「長老ヨハネ」が書いていることが分かります。この「長老」は単なる地方教会の聖職者ではなく、広範囲の教会に対して忠告や訓戒をする特別な権限を持っていました。彼はイエス・キリストの直接の弟子であり、初代クリスチャンと次世代を繋ぐ重要な役割を担っていたのです。
ところで、この手紙の冒頭にある「選ばれた婦人」とは、いったい誰のことを指して言っているのでしょうか?一つには、イエスの母マリアを指すという説があります。ヨハネ福音書の19章には、十字架のイエスが愛する弟子ヨハネに「見なさい。あなたの母です」と言い、ヨハネがイエスの母を自分の家に引き取った、と記されています。
次に、『ヨハネの手紙二の1節』に書かれているように、「真理を知っている人々の集まり」、つまり「愛する教会」に宛てて書かれた手紙であるということも知って頂きたいのです。この表現は個人を指すのではなく、「イエス・キリストにある教会」、「父なる神に仕える母なる教会」を意味していると考えられます。手紙の中で「あなたの子供たち」「わたしたちが」「あなたがたに」と複数形で語られていることがその証拠です。当時はキリスト者への迫害があり、手紙が敵対者の手に渡ることを恐れ、あえて宛先を不明瞭にしたのかもしれません。
『ヨハネの福音書7章』でイエス様は謎めいた言葉を語られました。「あなたたちは、わたしを捜しても、見つけることがない。わたしのいる所に、あなたたちは来ることができない」と。これは、十字架の死と復活の後、天の御父のもとに帰られることをイエス様が、暗示しておられる言葉です。歴史上、ユダヤ人は「ディアスポラ(離散の民)」として世界中に散らされました。イエス様も、パレスチナを去って弟子たちの手の届かない、遠くへ行ってしまわれるということを示唆されていたのでしょうか。
一方で、イエス様は「求めよ、そうすれば与えられる」「捜せ、そうすれば見つかる」(マタイ7:7)とも言われました。この矛盾する二つの言葉の意味を、イザヤ書は「あなたがたは、主にお会いすることができる中に、主を尋ねよ」(イザヤ書55章6節)と解き明かしています。私たちの人生の特徴は、時間が限られている、ということであります。「時のある間に」行動しなければ、その機会は失われてしまいます。イエス様の肉体も弟子たちの元から見えなくなり、彼らが急いで墓に行った時には、すでに「空」になっていました。
長老ヨハネは「真理のため」に教会を愛しました。キリスト教の愛「アガペー」は「価値なきものを愛する」もので、エロスの対極にあります。これは感情や熱情ではなく、「絶えることのない不屈な善意」です。相手がどうであれ、常にその人のために最高の善を求める態度であり、「すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える愛」なのです。対照的に、エロスの愛は「占有」を目的としており、時に人を和らげて骨抜きにしたり、破滅へと導くこともあります。愛する兄弟姉妹の皆様、今日はヨハネの福音書と手紙から、神様の愛とその実践について共に考えましょう。キリスト教の愛は、常に他者の最高の幸福を探し求め続ける愛です。これはあらゆる困難と苦労を自ら引き受ける愛であり、同時に私たちの果たすべき「義務」でもあります。
長老ヨハネは、第一の手紙で、神の受難、犠牲、そして想像を絶する寛大な愛について語った後、こう教えています。「愛する者たち、神がこのようにわたしたちを愛してくださったのであるから、わたしたちも互いに愛し合うべきである」(ヨハネ第一4:11)。私たちキリスト者は、神が愛する人々に愛を示すことなしに、神の愛を受け入れることはできません。神の愛は「人間愛の義務」を私たちに課します。神が私たちを愛してくださったように、私たちも同じく寛大な犠牲的愛をもって人々を愛するべきなのです。ヨハネの手紙一の4章10節にも「わたしたちが神を愛したのではなく、神がわたしたちを愛して、わたしたちの罪を償ういけにえとして、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります」と記されています。
また『ヨハネの手紙二の3節』には注目すべき挨拶があります。「恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちにわたしたちと共にあります」。他の使徒たちが「〜があるように」と願いや祈りの形で挨拶するのに対し、ヨハネは「〜あるであろう」という宣言をしています。これは神の約束に対する揺るぎのない確信の表れなのです。ヨハネが手紙を送った教会には様々な問題がありました。真理のうちを歩む人々もいれば、そうでない人々もいたのでしょう。分裂の危機もあったことが窺えます。こうした状況に対して、ヨハネは「愛」という解決策を示しました。これはイエス・キリストの教えに基づくものです。「互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなたがたがわたしの弟子であることを、すべての者が認めるであろう」(ヨハネ13:34-35)。
愛こそが人間関係の破壊された状況を修復できる唯一の手段です。非難や批評は憤慨や悪意を生み、議論や論争は断絶を深めるだけです。しかし愛は人との断絶を償い、失われた関係を回復することができるのです。私たちが神を愛している証拠は、兄弟姉妹たちを互いに愛することにあります。母の愛にも優る、イエス・キリストの愛に生かされて、残された人生を全うしていきましょう。